品質究理部
2018年入社
Kさん


未知の商品に対する、今までにない検査法を開発。食の未来と安全に貢献する仕事
もともと製薬会社で医薬品の安全性評価を担当してきましたが、会社都合による配置転換があり転職を決意。安全性研究の道を歩み続けられる日清食品グループへの入社を決めました。医食同源とも言いますから、人の身体に影響のあるものとしては医薬品と食品は共通点も多い分野です。他方、ミッションは大きく変化。前職ではどちらかというと決められた試験をこなすことが主業務でしたが、現在は新しい検査法の研究開発が主な業務となりました。
日清食品グループも力を入れるフードテックによって新たな食品や食べ物が世の中に登場してくる中で、これまでの人間が重ねてきた食経験ではカバーできない、未知の物質に対する安全性評価が必要になります。会社にとって、ひいては世の中にとっても今後必要とされる研究課題です。

一人ひとりが研究を主導し
課題解決に結実するやりがい
現在の品質究理部の研究分野は大きく分けて、新規危害物質の探索、食物アレルゲン、動物実験代替法の3つ。私は動物実験代替法の担当で、細胞実験やコンピュータ予測を活用した安全性評価を進めています。一人ひとりがテーマを持ち、主体的に研究を進めるのが当部署のスタイル。研究の進め方は個々人にゆだねられており、自由度高く動ける環境です。
私も入社間もなくから、エポキシ脂肪酸の研究を主導。培養細胞を用いた毒性評価により健康への懸念は低いことを論文にまとめ、製造現場で用いられている既存の指標で管理可能であることも明らかにしました。このように自分の研究が短期間で会社や世の中の課題解決につながることは、メーカーで研究を行う大きな魅力です。

スピーディな判断も求められる研究の現場。大切なのは人との連携
一方、結果が現場へ直結するからこそ、スピーディな判断が求められる点はこの仕事のむずかしさでもあります。例えば有害である可能性が否定できない新たな物質が見つかった場合、製造ライン停止の判断にもつながり得ますから、安全性の回答は一刻を争います。製造現場や管理部門がどんな情報を求めているか確認したり、多様な知見を持つ同僚たちに協力を仰いだりと、課題を乗り越えるためには部署や研究領域を超えたコミュニケーションが必要です。
また、大学との連携が密なのも当社の特徴。共同研究の実施や、研究室発の技術を応用することも多くあります。iPS細胞などで身体の機能を再現してADME試験(物質が体内を吸収・分布・代謝・排泄されるかを解析する試験)を行うなど、今後も研究者の意見や最先端の技術を取り入れながら新しい評価法を開発していきたいですね。また、安全性に関わる技術は自社だけでなく世の中で共通して同じような評価ができることが大事です。そのため、開発した技術を学会発表や論文などで外部に発表しています。その成果の一部は学会表彰も受けるなど、当社の安全研究に対する取り組みは外部からも高く評価されています。将来的には外部も巻き込んで食品業界全体の社会課題の解決の取り組みに発展させていきたいです。
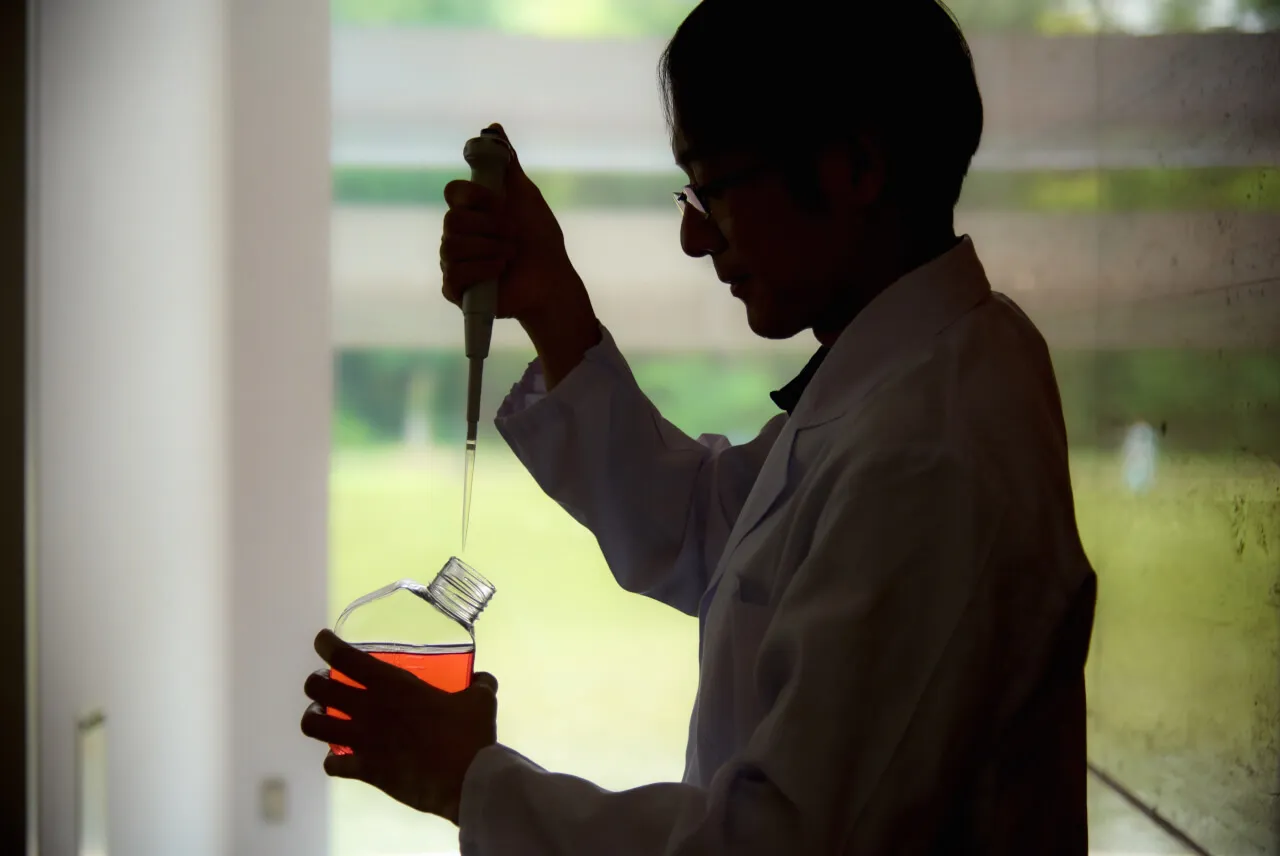
やりたいことに没頭できる環境で
最前線での研究を生涯のキャリアに
日清食品グループは「おいしい」「楽しい」を大事にしていますが、それを支える基盤が「安全」であり、何よりも「安全」を優先する会社です。そのため安全研究のためのインフラ投資にも積極的。質量分析装置など1台何千万円もする設備を多数保有しており、研究を滞りなく進めることができます。
また、キャリアパスとしても2024年春からプロフェッショナルコースが新設され、管理職ではなく専門分野を突き詰める道も選べるようになりました。私自身、制度導入時からこのプロフェッショナルのキャリアを選択。研究畑で手を動かし続けたいという想いが叶いました。やりたい研究ができる自由で充実した環境のもと、新しい試験法を追究し続け、「安全性評価といえばKさん」と言われるようなこの分野の生き字引になることが私の目標です。
